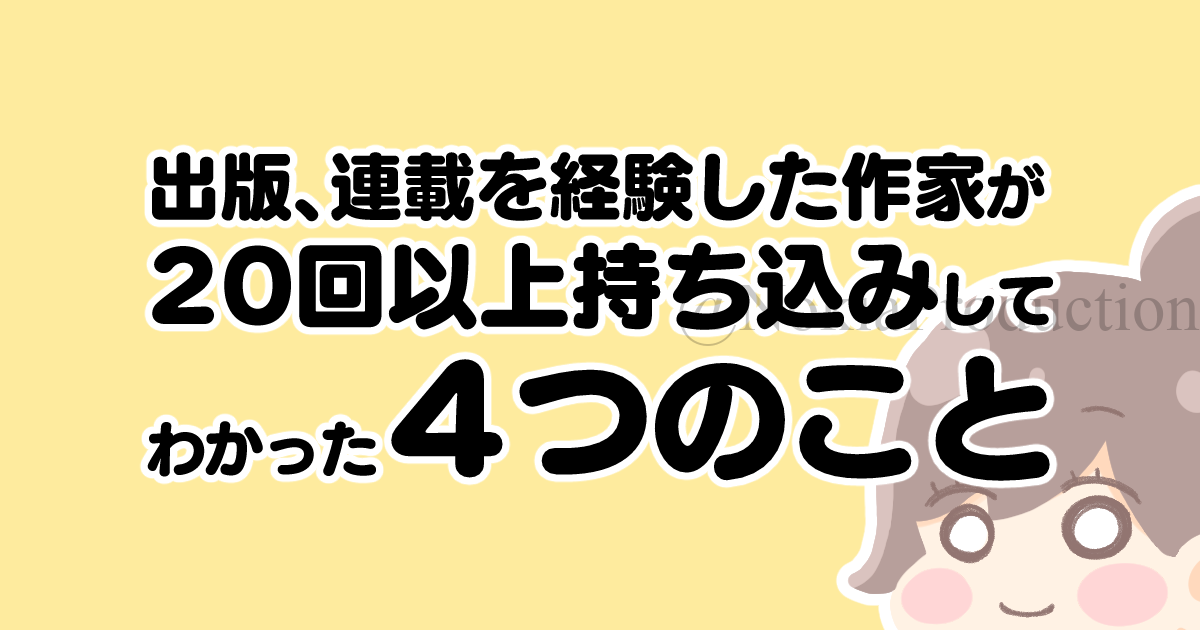漫画家3年目の乃樹愛(のきあ)です。売れっ子ではありませんが、エッセイ本の出版(3刷目)とweb媒体で週刊連載(1200万views)をそれなりに経験してきました。
その間に何度も何度も持ち込みを経験して、たくさんの失敗や気づきを得ました。今回の記事は、その備忘録です。まだ持ち込みをしたことのない方はもちろんのこと、私と同様に持ち込みをして苦しんでいる人にも、この記事が何かのお役に立てれば幸いです。
漫画の「ゴール」を考える。
はじめに言っておくと、漫画は自由です。複数の絵でストーリーが紡がれていれば、それはもう漫画です。 SNSのマンガ事情を見ていると分かるように、吹き出しがあろうがなかろうが、コマが何個あろうがなかろうが、1ページしかなかろうが…なんでもいいのです。 漫画というのは、それだけ自由です。
しかしながら「漫画を仕事にするために、雑誌やweb媒体の〇〇に載せたい!」となってくると、制限がかかってきます。 わかりやすいものだと、原稿のサイズや解像度、規定ページ数などなど…これだけでも自由気ままに描くことはできなくなります。人によってはストレスです。
漫画を「仕事」にしたいなら…
「それでもいいから、自分の漫画を媒体に載せてもらいたい!」というのであれば、担当さんを探すために今からお話しする作品の持ち込みや漫画賞に応募するなどをします。
最近の持ち込みはTwitterのDMで編集さんが直接募集していたり、コロナ禍ということもあり各雑誌の公式HPなどで「オンライン持ち込み」を実施していたりすることが多いです。自分の漫画を載せたい・気になる媒体のHPをチェックしてみましょう。
また、雑誌などに載せるこだわりはなく「とにかく漫画で収入を得たい!」という方は、自分で電子書籍にして電子書籍の代理店(おすすめはナンバーナインさん)にお願いするのも選択肢の一つです。
ただし、この方法は原稿を描いたらもらえる原稿料ではなく、売れた分だけもらえる印税となるので、メインの収入源になるまでは少し時間がかかる場合が多いです。
持ち込みは二箇所以上すべし。
まず持論ですが、持ち込みは二箇所以上するべきです。 理由として、同じ作品を持ち込んでいるのにもかかわらず、編集さんによって見方が全然違うことが結構あるからです。
それに、もし「目の前の編集さんの意見がすべてだ!」と思って持ち込んで、悲しい言葉を投げかけられて筆を折るようなことがあったら…それは本当にもったいないことです。
例えば、編集Aさんは「〇〇という部分がよくない」と言っていたのに、編集Bさんは「〇〇はいいけど✖︎✖︎がよくない」となることは多々あります。そうすると「結局どっちがダメなんだ…」と負のループに入り、悩み始めてしまうわけです。それを避けるためにも、ひとつの作品をいろんな編集さんに見てもらって、さまざまな意見を聞いてみるのがいいと思います。
逆に言えば、別の編集さんから、同じダメ出しが出てきたり、似たようなダメ出しが続くようになってきたら「原因がはっきりしているサイン」です。 指摘された部分をもう一度見つめ直してみるといいですね。
絵が下手でも、面白ければいい。
特に初めて持ち込みをする時。よっぽど絵が上手い人でない限り、大抵は絵の指摘をされると思います。先に言っておくと、絵は上手いに越したことはありません。絵が上手ければ、それだけで読者に「お、これ絵が綺麗だな。見てみよう。」と思ってもらえる確率は上がりますので、認知度が高くなるし、自分の武器になるということです。
ですが「絵の上手さ」というのは上限がありません。「誰よりも絵が上手くなってから漫画を描こう!」では、一生漫画は描けません。 それに「絵が上手くなかったら終わり」でもないのが漫画の面白いところです。絵が下手でも、売れている面白い作品はたくさんあるからです。
私が持ち込みをして導き出した「最低限の画力の基準」は「自分が伝えようと思ったものが相手に同じように伝わっているか」です。 極端な例ですが、犬を描いた時に犬に見えるかどうか。悔しい表情を描いた時に悔しそうに見えるかどうか。 伝えたいものが伝わっているのであれば、最低限の画力は備わっていると考えていいと思います。
編集さんの示す「画力」とは
私も持ち込む度に「絵をもっと頑張ってほしい」「画力が足りないね」と言われ続けて、絵を描くのがつらくなるほど、めちゃくちゃ悩んでいた時期がありました。
そういう時はアドバイスをくれた編集さんの示す「画力」が「デッサン力」を指しているのか、「演出力・構成力」を指しているのか、もっとツッコんで聞いてみるといいでしょう。
「デッサン力」と言われた場合は、デッサン本やなどを用いて人体のデッサンやスケッチ、クロッキーをやってみましょう。遠回りに感じるかもしれませんが「急がば回れ」です。私が担当さんにおすすめされた本のリンクを置いときます。(『人を描くのって楽しいね!』は本当にいつも使ってます)
下にある左の絵は当時の担当さんからデッサンを教わる前。右の絵はデッサンを教わってから3か月後に描いた同じ絵です。全然別の絵に見えますよね。私は担当さんに言われるまでデッサンを全く勉強してこなかったんですが、もっと早くやればよかったと本当に後悔しています。
漫画は「人物の感情」を描きます。感情は必ずしも顔だけに出てくるわけではありません。感情を丁寧に描くためにも、人体構造の勉強はやっておいて損はないです。
また「演出力」や「構成力」と言われた場合は、持ち込んだ雑誌の作品を見てみたり、いろんな漫画を読んでみて、コマ割りを勉強してみるのがおすすめです。(こちらの本もおすすめです。東京ネームタンクの講師の方が書いています。)
いい漫画は、それだけ演出力と構成力が桁違いです。 余力があれば、その編集さんが認める画力の高い漫画を聞いてみるのもいいと思います。はじめのうちは自分の画力との差に愕然とすると思いますが、勉強になったと思って冷静に受け止めましょう。現状を受け止めて正しく前進することができれば、必ず今以上にいい絵が描けるようになります。
ラーメンなのか、クレープなのか。
最近はオールジャンルを受け付けるweb媒体が多くなってきたので、どんなジャンルでも歓迎されやすいです。(その分競争率も高いですが…)
しかしながら、web・雑誌媒体問わず、どこでも必ず「看板商品」というものが存在します。
例えば、雑誌Aがラーメン屋だとしましょう。雑誌Aの看板メニューは「とんこつラーメン」です。 となると、同じとんこつラーメンで勝負するのは難しいわけです。「うちにはもうあるから…」となって、連載化は難しくなってしまう。 そこで、ラーメン屋で売れそうな醤油ラーメンや塩ラーメン、または餃子のような作品を持っていく必要があるわけです。
ここで仮に、タピオカやクレープのような作品をラーメン屋さんに持ち込んだとしましょう。そうすると「これはこれで美味しいけど、うちでは売れないんで結構です…」となってしまいます。
もちろん、これは確率の話なので、タピオカやクレープを採用してくれるラーメン屋さんも探せばあるとは思いますが…それなら、最初から採用してくれそうなケーキ屋さんやデザート屋さん、またはビュッフェのお店に持ち込む方が「あ!これ欲しかったんだよね!ありがとう!」と採用される確率が圧倒的にあがる、というわけです。
そのことに気づかないまま「どうして私のクレープはラーメン屋さんでウケないの…」「どうして俺のラーメンはクレープ屋でウケないんだ…」と悩んで描けなくなる人はとても多いです。
自分の料理(作品)が、どのお店(媒体)に合っているか。
「自分の作品がどこの雑誌と合っているのか」「合っている雑誌に持ち込めているのか」を見つめ直すことは、とーーーっても大事です!ラーメンの良さはクレープ屋さんよりラーメン屋の方が分かるし、クレープの良さはラーメン屋さんよりクレープ屋さんの方が分かります。(ディスってるわけじゃありませんよ!)
もし「自分の作品に合う雑誌がわからない」という方は、ぜひ東京ネームタンクの「持込先・進路相談」を活用してみてください。 さまざまな漫画媒体を網羅している東西サキ先生という方が、その作品に向いている媒体を教えてくれます。
アドバイス通りじゃダメ。
最後に。編集さんに気に入られるために、言われたことをそのままやってもダメです。作品というのは、編集さんの先にいるまだ見ぬ読者に向けて作品を描くべきです。
理由は、編集さんのいう通りに描けば連載させてもらえるというわけではないし、誰かの言われた通りに渋々描いた作品が読者の心に響くわけがわけないからです。
私は少し前にそれを9回やって心が折れかけました。その編集さんに認めてもらうことばかりを考えて、その先にいる読者が全然見えていなかったんです。(9作のボツネームはこのブログに残したので興味がある方は見てみてください。迷走具合がすごいです。)
では、何のために持ち込むのでしょうか。
編集さんは「ヒント」を持っている。
編集さんの言葉は自分の作品をより良くするための「ヒント」です。「正解」ではありません。その「ヒント」から「答え」を導き出すのは、他の誰でもない作家である自分自身です。
そもそも、もし編集さんが「正解」を知っているのなら、この世はヒット作だらけになります。ヒット作は誰にも予想がつかないのです。 私はこれらのことに気づくのに何年もかかってしまいました。
長々と書いてきましたが、私自身もまだまだまだまだ未熟な漫画家です。人様にいろいろと言える立場の人間ではありませんが、この記事が未来の自分やどこかの作家さんのお役に立てればいいと思って書きました。最後までご覧いただき、ありがとうございました。